せっかく冷蔵庫を買い替えるなら電気代を安くしたい!
誰もが当たり前のように思うはずですが、
電気代が安くなるモデルはほとんどありません。
知らずに買うと後悔するその理由と対策を紹介いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。
2013年製と2023年製の省エネ性能の違い

| 2013年日立製475L | 2023年日立製485L | |
| 年間消費電力量 | 180kw | 276kW |
| 基礎電気代(27円/kw) | 4860円 | 7452円 |
| 燃料費調整額(5.13円/kw) | 923円 | 1416円 |
| 再生可能エネルギー発電促進賦課金(3.45円/kw) | 621円 | 952円 |
| 電気代合計 | 6404円 | 9820円 |
まさかの大幅劣化!しているように見えます。
同じkw単価で計算しているので、昨今の電気代高騰は関係ありません。消費電力量もメーカーが公表している数値であり、特別な機能は全てオフの状態での数値です。
でも実際のところ、ギリギリですが電気代が安い冷蔵庫は2023年製の方です。
あべこべの原因は、2015年2月に消費電力量の「基準」が大幅に変更されたため。
そのせいで、それ以前のモデルを使っている人にとっては、
きちんと電気代が安くなるモデルを選ぶことがとても難しい状況になっています。
2013年製冷蔵庫の本当の電気代

2015年2月より前に発売された冷蔵庫は、簡単に言うと「ゆるゆる」な基準で電気量が計算されていました。
| 2013年日立製475L | 2023年日立製485L | |
| 年間消費電力量 | 180kw→推定283kw | 276kW |
| 基礎電気代(27円/kw) | 7641円 | 7452円 |
| 燃料費調整額(5.13円/kw) | 1451円 | 1416円 |
| 再生可能エネルギー発電促進賦課金(3.45円/kw) | 976円 | 952円 |
| 電気代合計 | 10068円 | 9820円 |
2015年2月より前の「ゆるゆる」な基準
- 電気量を測定する環境温度が、現在の基準より2.6℃低い
- 冷蔵庫の開閉時間が、現基準の60秒でなく10秒しかない
- 冷蔵庫に投入しておいて一緒に冷やす物が、現基準の12g/Lでなく6.7g/Lと少ない
- 逆に冷凍庫には現基準の4g/Lより多くの冷却物6.25g/Lを投入(最初は水だが凍れば消費電力を抑える効果がある)
結果として、401L以上の冷蔵庫は平均で約36%も電気量が少なく計算されていました(日本電機工業会より)。
でも…………あれ?
基準を合わせて比べても、全然電気代が安くならない???
その点についても、理由があります。もしもお店に行って店員に聞くと「基準が厳しくなっただけだから」とか「電気代が高騰しているからその影響」とウソを言われてしまう可能性がありますが、きちんとお話いたします。
本当の定格容量も異なる

現行の基準が正しいとすると、2023年製の485Lは485Lです。当たり前です。
しかし、2013年製の475Lは違います。誤りです。実際には減ります。
2015年2月より前のモデルは、食品を置くことが不可能な「冷気ダクト」まで容量に含んで表示されていたからです。
冷気ダクトの大きさはモデルごとに違いますが、冷蔵庫の上から下まで(冷蔵室も野菜室も冷凍室も)ぐるりと配管されているので、およそ10%前後の容量を占めています。
つまり、2013年製の475Lは現基準では427L相当。基準を合わせて電気代が変わらないようでも、2023年製の方がより多くの食品を冷やすことができます。
ただし、現基準で427Lの冷蔵庫を買えば電気代を安くできるかというと、
逆です。高くなります。
冷蔵庫は小さくしても電気代は安くならない

| 2022年日立製401L | 2023年日立製485L | |
| 年間消費電力量 | 273kw | 276kW |
| 基礎電気代(27円/kw) | 7371円 | 7452円 |
| 燃料費調整額(5.13円/kw) | 1400円 | 1416円 |
| 再生可能エネルギー発電促進賦課金(3.45円/kw) | 941円 | 952円 |
| 電気代合計 | 9712円 | 9820円 |
小さくした方が安いじゃないか!(※みせかけです)
基準は同じなので、基準の通り1年に1回しか冷蔵庫の扉を開けなければ表の通りですが、普通は毎日複数回開けます。
そして、401Lはメインの冷蔵室がフルオープンタイプですが、485Lは左右どちらかだけを開けられるハーフタイプ。冷蔵室の冷気が逃げ出しにくい扉を採用しているのは485Lの方です(このモデルに限らず、容量が大きなモデルはほとんどハーフタイプ。逆に小さくなるとフルオープン率が高くなる)。

扉の開閉により具体的にどれだけの冷気が逃げ出し、再度冷やすためにどれだけの電気代が掛かるのかは公表データは1つもありませんが、401L冷蔵庫が初めて電源を入れて庫内が冷えるまでに81円相当の電気量を消費するので(冷凍室含む)、1日10回、1年で3650回ほど開けて冷気が逃げればそれなりの電気を消費するに違いありません。
極端に小さくすれば電気代は安くなる?

| 2022年日立製154L | 2022年日立製401L | 2023年日立製485L | |
| 年間消費電力量 | 304kw | 273kw | 276kW |
| 基礎電気代(27円/kw) | 8208円 | 7371円 | 7452円 |
| 燃料費調整額(5.13円/kw) | 1559円 | 1400円 | 1416円 |
| 再生可能エネルギー発電促進賦課金(3.45円/kw) | 1048円 | 941円 | 952円 |
| 電気代合計 | 10815円 | 9712円 | 9820円 |
1人暮らし用の154Lまでサイズダウンすると電気代は高くなります。
最大使用電気量は154L→185W、401L→232W、485L→270Wなので、初めて電源を入れたときは大きな冷蔵庫の方が電気をたくさん使います。
でも実は、「維持」で使う電気量は485Lタイプでも30W程度しかありません。
- 冷えた後は、食品自体が保冷剤代わりになる
- 大きな冷蔵庫ほど保冷剤(食品)が多くて温度を維持しやすい
- 逆に小さな冷蔵庫は、扉を開けると逃げ出す冷気の割合が大きくて維持しにくい(大きな冷蔵庫は庫内の冷気が多いので、同じように逃げ出しても全体としての割合は小さい)
扉の開閉頻度や取り出しやすさを考慮して、冷蔵室は50%程度、冷凍庫は70~80%まで食品を入れておくともっとも効率的に冷蔵庫を使うことができます。
結局、節電効果の高い冷蔵庫ってどれ?

27円/kwで計算した際に、現在の基準で基礎電気代が年間7000円を下回るモデルのみ紹介いたします!
なお、現在販売されている冷蔵庫は1000機種以上ありますが、該当はわずか10機種ほどしかありません。
600Lクラス
年間消費電力量の目安はどちらも252kw。参考として登場した2023年日立製と比べても10%ほど省エネになります。
どちらのモデルも野菜に潤いを与え、肉や魚の表面だけを凍らせて鮮度を保つ技術を搭載。
個性としてはパナソニックは食品をいち早く凍らせる急速冷凍機能があり(使うと消費電力は増える)、東芝はタッチオープン機能(手やひじで押して開けられる)やBluetoothスピーカー内蔵(誰も冷蔵庫から音楽を聴きたいとは思いませんが……)。
電気を多く使うモデルほど多機能で個性が出ますが、省エネ特化型は必要な機能だけに絞られているため(?)、大きな差は出ません。
Bluetoothスピーカーが不要なら、その分だけ少し安いパナソニック製がおすすめです。
500Lクラス
500Lクラスでも省エネに特化したモデルがラインナップされているのはパナソニック(256kw/年)と東芝(245kw/年)のみ。
多機能を詰め込む方がメーカーも勝負しやすいため、本当に省エネ性能が高いモデルはかなり限定されます。
400Lクラス
年間消費電力の目安は上から順に、252kw/250kw/249kwです。
このサイズでもシャープ製は両開きドアを採用しているので、冷気が逃げ出しにくくておすすめです。
200~300L
1機種もありません!
全てのメーカーで年間の電気代は7000円超え。このサイズは冷却効率が悪く、400L以上を購入する方が電気代は安くなります。
100L
ハイアール製が239kw/アイリスオーヤマ製が207kwの年間消費電力量。
ここまでサイズが小さければ金額が安いモデルがあるものの、100Lクラスはこの2モデルのみ。
一人暮らしで生活費を抑えたい方向けのモデルです。
番外編700L
年間電気代の目安が6000円台ではないものの、700Lクラスの需要が増えているので、その中でも比較的省エネのモデルを紹介します。
年間消費電力の目安は310kw。基礎電気料+燃料調整費+再生エネルギー費=11029円と少し高くなりますが、食品をまとめ買いすれば食費を下げられるので、選択肢の1つとしては十分におすすめです。
あまり知りたくない裏話

年々技術が進歩して省エネ性能が上がっているはずなのに、現実には電気代が安いモデルが非常に少ないです。
そのワケは、冷蔵庫は年々スリム化しており、組み込む冷却システムが小型化して冷却効率が落ちているからです。
従来より省スペースで大きな容量の冷蔵庫を置けるメリットは確かにありますが、そればかりがアピールされています。冷蔵庫はずっと昔からある製品なのに本体価格が安くならない理由も、小型化のコストの影響が大きいです。
2011年以前に買った冷蔵庫を使っているなら、おすすめモデル以外に買い替えても節電効果を期待できる

冷蔵庫のスリム化は2015年頃からであり、2012~2014年までは省エネ特化の冷蔵庫が主流でした。
2011年に東日本大震災が起こり、直後に大規模な電力不足。生活においても経済においても節電が至上となり、翌2012年に発売された家電製品は急激に省エネ性能を高めたモデルばかり。その翌年も翌々年も節電意識が高い状況が続いていたので、当時の冷蔵庫は現在と比較しても十分に省エネ性能が優れています。
つまり、2012年製以降の冷蔵庫を使っている方は、急いで買い替える必要はありません(10年前との比較で紹介しておきながら、ですが)。
2011年以前のモデルを使っている方だけ、当時の省エネ特化ではなかったモデルから現在の省エネ性能が高いモデルへの買い替えをおすすめします(経年劣化により冷却効率が新品時より落ちているはずでもある)。




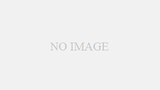

気軽なご相談はこちらから!